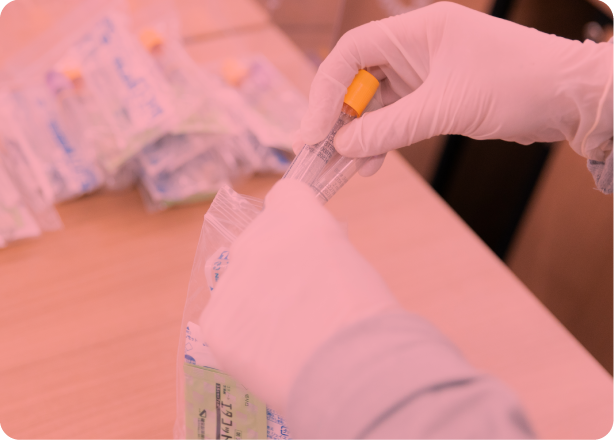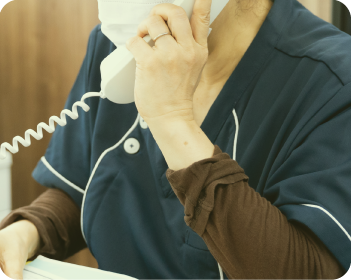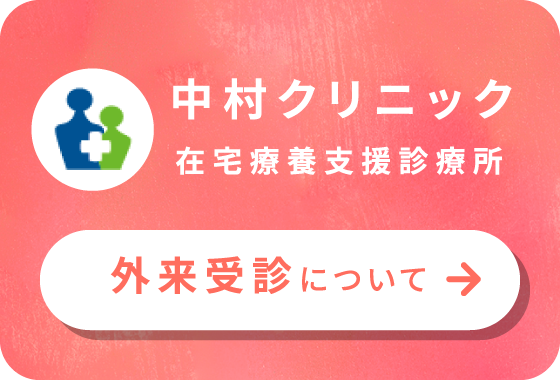おはようございます。医師の中村です。
今日は「在宅医療における家族介護者の重要性」について書きたいと思います。
患者さんが在宅での療養を希望する場合、重要になるのが家族介護者の存在です。
主たる介護者という役割以外にも、療養場所の選択や治療方針などにも
強い影響を持つことがさまざま研究で指摘されています。
在宅での療養を希望しているにもかかわらず、
在宅療養の継続を断念した事例を検討した文献を紹介します。
渡辺らは、1日22時間以上人工呼吸器を装着し在宅療養をした
神経難病患者20名について在宅療養の継続ができなくなった直接的理由を調査しました。
患者の内訳は、男女各10名、年齢51-82歳、平均69.9±7.9歳、
神経疾患は筋萎縮性側索硬化症18名、肢体型筋ジストロフィー1名、
進行性核上性麻痺1名でした。
経済的理由以外に、介護者の健康問題
(例えば介護者が病気になったあるいは入院した)、
介護者のストレス(抑うつ的な精神状況、身体介護へのストレス)、
家人の協力が得られなくなったというように、
家族介護者の問題で在宅療養の継続が困難になったと報告しています(2014 渡辺)。
市原らは、在宅での療養を断念し、
病院での看取りとなった88名の再入院の理由について報告しており、
家族の希望が42名、本人の希望が23名、症状悪化が15名であった。
家族が不安になり入院を希望したケースが多かったと報告しています(2013 市原)。
看取り数の多い(年間看取り数20名以上)在宅特化型診療所から、
在宅緩和ケアを受けた終末期がん患者を対象とした佐藤らの報告では、
がん患者352名のうち在宅中止が63名(18%)であり、
家族に不安・抑うつがある(オッズ比4.1)、
主介護者の介護頻度が少ない(オッズ比6.8)といった
家族介護者にかかわる要因が中止要因として指摘されています(2015 佐藤)。
また、病院側からみた場合、つまり病院から在宅への移行を
困難にさせた理由を調査した報告もあります。
渡部は、緩和ケア病棟の入院患者について調査しており、
自宅での介護や看取りに対する家族の不安、独居・同居者の介護力不足、
家族関係の問題を、在宅移行困難例として報告しています(2007 渡部)。
田邊は、終末期がん患者の在宅移行断念例について調査し、
家族の介護力、本人の意思、在宅環境調整・連携以外に、
家族の介護力、家族との関係性を要因として報告しています(2011 田邊)。
これらの研究からは、患者さんが在宅での療養を継続できるかどうかは
家族介護者に関わる要因が大きく、
そもそも在宅療養を開始できるかどうかも、
家族が重要な鍵を握っていることがわかります。
当院でも患者さんのケアはもちろんですが、
ご家族のケアも同じくらい大切だと考えています。
参考文献
市原利晃(2014)「在宅看取りの現状と検討」『ホスピスケアと在宅ケア』21(3)。
佐藤一樹(2015)「在宅緩和ケアを受けた終末期がん患者の在宅診療中止の関連要因」『Palliative Care Research』10(2)。
田邊蘭(2011)「退院支援における転帰におよぼす影響要因の検討 終末期がん患者への支援経過分析より」『関西電力病院医学雑誌』43。
渡辺千種(2014)「人工呼吸器を装着した神経難病患者が在宅療養継続困難となる要因の検討」『難病と在宅ケア』20(5)。
渡部芳紀(2007)「緩和ケア病棟における在宅移行困難症例の検討 緩和ケア病棟カンファレンスから抽出された緩和ケアの課題とその対策に関する考察」『三友堂病院医学雑誌.』24(1)。